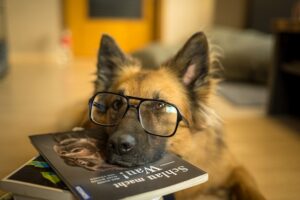vol.677【実践コラム】シンジケートローンと協調融資について

…手数料とコベナンツの重さを避け、資金コストと経営自由度を守る視点が重要です。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
新工場建設等、複数行から大型の資金調達を行う際に、銀行側から「シンジケートローン(SL)でまとめましょう」と提案されることがあります。確かに契約一本化や期中管理の簡素化は魅力です。しかし中小企業にとっては、アレンジャーフィーと厳格なコベナンツ(財務制限条項)が大きなハードルになります。個人的には、総合的に見て、同じ複数行スキームでも「協調融資(コンソーシアム融資)」を推奨します。
以下では、その理由と協調融資を円滑に進めるコツを整理します。
1.アレンジャーフィーは「見えない利息」
シンジケートローンを組成すると、調達額の1~3%程度のアレンジャーフィーと、年次エージェントフィーが発生します。仮に10億円を調達すれば数千万円の一時コスト、加えて毎年数百万円の維持費が必要です。協調融資であれば払わなくても済むコストをわざわざ負担するかどうかが最初の分岐点です。
2.コベナンツは経営の「足かせ」になりやすい
SLでは参加行平等を担保するため、パリパス条項や財務コベナンツが細かく定められます。典型的には「自己資本比率○%以上」「債務償還年数○年以内」「主要役員の変更は事前承認」など。違反すると全行が一斉に期限の利益を喪失させる権利を持ち、資金繰りが良好でも契約変更を迫られるリスクがあります。事業環境が読みにくい中小企業にとって、経営の自由度を引き下げる制約は避けたいところです。
3.協調融資の「煩雑さ」は工夫で緩和できる
協調融資は行ごとに契約を結ぶため、担保設定や返済スケジュールが複線化しやすいのは事実です。しかし、以下の3点を押さえれば管理負荷は大幅に下げられます。
1)リードバンク方式
メイン行を窓口とし、他行条件も基本的に追随形式で揃える。
2)共通条項表の作成
返済条件・担保順位・財務指標を一覧化し、全行と共有。修正はこの表だけに反映させる。
3)年1回の共同面談
決算後にメイン行主催で参加行を招き、事業報告と次年度計画を一括説明。バラバラの面談を減らす。
これにより「契約は行数分ですが、運営は実質一本化」という体制が実現します。手数料ゼロの協調融資と、費用の伴うSLの差額が毎年のキャッシュを守ることを考えると、手間をかける価値は十分あります。
4.判断フロー(簡易チェックリスト)
- 調達額が5億円を下回るか?
→ はい:協調融資で十分対応可能。 - 参加行は3行以内に収まるか?
→ はい:協調融資の管理負荷は限定的。 - 社内外に財務人員が確保できるか?
→ はい:SLの管理簡素化メリットは限定的。 - 事業計画に「柔軟な増額」より「手数料節約」を優先したいか?
→ はい:協調融資向き。
3つ以上「はい」があれば、協調融資を選んだほうが総コストは低く抑えられる可能性が高いと言えます。
■まとめ
- アレンジャーフィーとエージェントフィーは「隠れ金利」です。規模が大きくない中小企業には無視できない負担になる可能性があります。
- シンジケートローンのコベナンツは経営の自由度を縛ります。環境変化の激しい中小企業ではリスクが高いと考えます。
- 協調融資でもリードバンク方式と共通条項表で管理は簡素化可能です。
費用を抑えつつ、制約を減らし、必要な資金を確保する。この3点を優先するなら、中小企業には協調融資が現実的な選択肢となります。まずはメイン行に協調スキームの枠組みを提示し、手数料を掛けずに複数行をまとめる段取りを検討してみてください。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)